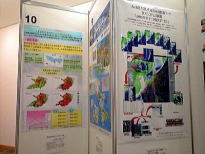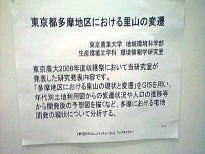研究室研修旅行
関東農政局茨城県那珂川沿岸農業
水利事業所実施
日付2009年7月30日~31日
我々「環境情報学研究室」は7月30日、31日の2日間に亘り研修旅行ということで茨城県那珂川沿岸の水資源施設を見学させていただきました。那珂川沿岸農業水利事業所の皆様方には総勢43名もの大人数を快く迎えていただけたことに改めて感謝申し上げます。なお以下に本研修旅行に参加した学生の感想文を掲載いたします。
h4 3年 田中 泰人 【2009年度研修旅行 事後レポート】 headline4
私たち環境情報学研究室室員一同は、研修旅行として7月30、31日の二日間にわたり農林水産省関東農政局那珂川沿岸農業水利事業地区内にある茨城県常陸大宮市の御前山ダムと小場江頭首工を見学した。
梅雨前線が離れたにも関わらず雨が心配される中、室員は朝から見学を楽しみに茨城県に向かった。当研究室は、主な学習内容としてGISを用いた広域情報処理やリモートセンシング技術などが挙げられるが、今回施設を訪れた目的は地域の農業用水確保のための水源や用水路建設の現場を知ることでGIS技術の活用可能性を発見することである。
研究室員一同は、まず水戸市内の那珂川沿岸農業水利事業所において、尾崎所長、野々村工事第一課長から事業内容、御前山ダムの仕組みや地域の農業用水への効果などの説明を受けた後に御前山ダムに向かった。移動中のバスでも本学OBである高木企画官、山田専門官から地図、写真を用いて那珂川沿岸に設置されている用水施設などを説明して頂き、目的地へ向かいながらも那珂川と御前山ダムの知識を深めていった。
研究室のゼミで、ある程度ダムについて学習していたものの、やはり実物を目の当たりにするとダムはとても大きく、一同は圧倒されていた。御前山ダムは現在も建設中の中心遮水ゾーン型ロックフィルダムで、堤体の盛立ては終了していた。高さは約52メートルで、茨城県内のダムでは高萩市にある小山ダムに次いで高く、茨城県内では初めての国直轄ダムとなっている。
今回、私たちはその建設中のダムの監査廊を特別に見学させていただいた。夏であるのにもかかわらず中はとても涼しく、階段を降りていくごとに気温は下がっていった。内部は中心に向かうほど斜面が急になっており、その斜面は見ると足がすくむほどであった。貴重な見学をさせていただいた後に私たちが向かった先は、江戸時代からの歴史がある小場江頭首工である。
ひたちなか市までの全長約30kmの小場江用水路の起点となる那珂川からの取水施設で、用水路の途中ではポンプ場を設け台地に水を供給している。頭首工はかんがい期の4月~9月は水門を閉じ取水するが、非かんがい期の10月~3月にかけてはサケが遡上する為にゲートを開放している
見学当日は雨のために那珂川は増水していたためにその流量は私の想像を超え、大量の水が頭首工ゲート周辺で渦を巻いていた。昔から洪水の被害を数多く受けるのもこれで理解ができた。これらダムと頭首工により自然の力に立ち向かい、かつては氾濫していた那珂川をうまく利用してさらなる農業の進展へと繋げていることに私は感動と希望を持った。我々、環境情報学研究室では、教室の中でパソコンを使用して情報を得ることが多いが、やはり現地に行き、実際の状況を見て真の情報を知ることが本当に情報を得ることであると気づかされた。
様々な経験を積むことが出来た研修旅行であったが、研究室員同士が勉強だけではなく、寝起きを共にすることで、より絆を深めることを出来たことが私個人としては何よりも嬉しく思える旅行となった。今回の研修旅行においてお世話になった「農林水産省関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所」の皆様にはこの場を借りて改めて御礼申し上げ、更なる発展、ご活躍を祈念します。
研究室所在
東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科
ジオデータサイエンス研究室(旧広域環境情報学研究室)
収穫祭 文化学術展示
テーマ「みんな大好き多摩川
~多摩川の変遷について~」
日付2009年10月30日~1日
Copyright 2024. Geodata Science Laboratory.